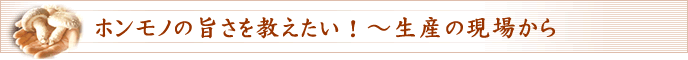|
川内村の某所にて、伐採の現場です。 このあたりは山の頂上のところ。村から許可をもらって、一年分の原木となる木を伐採します。主にクヌギ、ナラの木を伐採しています。 太さ10センチほどの木を探し、原木にするのですが、川内の木はみんな太くなりすぎて、細い木を探すのが大変だとか。 |
 |
「この見える山全部が川内の山なんだ。木はあまるほどあるんだから、他の川内の人がもっと原木しいたけを栽培してみたらいいんだ」 見渡す限り、全部が山。この豊かな大自然が川内の良さなんだなぁ。 |
 |
冬場はハウスの中を、古くなって芽が出ない原木を薪にして燃やし暖めます。常にハウスの中は20度。夜に薪をくべると朝まで一晩中燃えて暖めてくれます。 ハウスや暖房設備など、最初は設備が大変です。 「結構お金がかかる仕事なので、これから原木しいたけをやろうという人はなかなかいないねぇ。それに、手間もかかるしね。重い原木を棚に移す時は、菌が植えてあるところを痛めないようにと木を使うしね。大変なんだよぉ。」 ハウスの中が乾燥しすぎると芽が出ないので、2日に1回、水をかけなければなりません。 |
 |
「子どものように手をかけてやんないと、うまく育ってくれないから、大変だよ〜。毎年、毎年、勉強だねぇ。」 その年の天候や気温などに左右されるので、ハウス栽培でもうまくいかない時があるそうです。 タツさんの小さい体で、水分のタップリ含んだ原木を棚に一本一本入れていくのは、容易な仕事ではありません。幹夫さんと二人で1万本が精一杯。 「だから、立派な大きいしいたけができると、とてもうれしいんだ!!」 |
 |
贈答シーズンには、東京の子どもに送りたいとか、親戚に送りたいと求められる方が少なくありません。 「やっぱり、一度原木しいたけを食べて香りや味がわかっている人には、また、送ってくれって言われるよね。今の人は、原木より菌床栽培のしいたけばかり食べてるから、食べると違いがわかると思うよ」 ふっくらと丸くて厚みがあり、裏のヒダもきれいな原木しいたけを、たくさんの人に食べてもらいたいです。本物の味や香りをぜひ味わってもらいたいですね。 |
味と香りが違う!自然の味そのままの原木栽培しいたけを直販でお届け。阿武隈山系の森が育てた恵みの味、川内村の小林しいたけ。
 山盛りのしいたけ |
橋を渡り左に曲がると、小林さんの自宅、毛戸方面へと向かう。
そこからおよそ5キロ位あるのだが、途中の景色は写真集のような風景が見られる。私が出かけた時は紅葉の散り初めだったのだが、まだ残っているもみじや毛戸ダムの風景がとても美しかった。
小林さんが栽培しているしいたけの原木は、全部で1万本。
以前は、3万本もあったという。
毎日の作業は、主にご主人がしいたけの栽培管理をし、奥様が収穫やパック詰めをしている。商品は、ご主人が早朝5時に富岡町の青果市場に運ぶ。
 しいたけを育てる山の清水 |
ご主人に「体力的に大変ではないですか」と聞いてみたら、「大変だげど〜、この原木しいたけは、この辺では俺しかやってないから、やるしかねえんだ」と張りきって答えてくれた。
「大変な仕事だからこそ、やりがいもあるし、きのこもかわいく思えるんだぁ」とご主人。
お二人がしいたけ栽培を始めたのは今から30年前。最初から栽培がうまくいったわけではないそうだ。
なかなか大きなしいたけにならずに悩んだ時もあった。時には、不作の年もあった。
そんな時は、しいたけの産地、群馬県富岡市に研修に行き、いろいろと勉強を重ねた。試行錯誤しながら、ご夫婦お二人が、ここまでにするには大変苦労したそうだ。
シイタケ栽培には2通りの方法がある。
ナラやクヌギなどの木にしいたけの菌を植え込んで栽培する「原木栽培」、おがくずに米ぬかなどを混ぜて固めたものに植菌する「菌床栽培」 があるが、小林さんは「原木栽培」にこだわり続けている。
原木栽培をしているのは、双葉郡では2件しかない。
 かわいい赤ちゃんしいたけ |
見ると、上の段の原木に、収穫できるくらいの立派なしいたけがたくさんなっていた。下の段は、まだ赤ちゃんしいたけのようだった。
なぜこんなに成長の仕方が違うのかというと、暖かい空気が上にいってしまい、下に冷たい空気が溜まってしますから、とのこと。
ハウスの入り口付近に大きなストーブ(焼却炉?)が、あった。
これは、冬場にハウスを暖めるためのもので、燃やす原料は、使わなくなったしいたけの木を使うのだ。不要のしいたけの木をリサイクルしている。
しかも、このストーブからはパイプが出ていて、ホダ木の下をめぐるように土の中に半分うまっている。冬になると寒さが半端ではないので、下から暖めながら、室温を15℃位に保たないとしいたけがうまく育ってくれないそうだ。
このパイプを半分土の中に埋めるやり方は、小林さんが、長年しいたけを育ててきて独自に考えたやり方、とのことだった。
小林さんお勧めのしいたけ料理
- ●しいたけの網焼き
- しいたけの旨さを味わうのなら網かオーブントースターで焼くのが一番!
焼きすぎるとジューシーさがなくなるので注意して。
- ●しいたけのから揚げ
- しいたけの軸をとり、酒としょうゆを混ぜたもので下味をしっかりつける。
- 片栗粉をまぶし、たっぷりの油で揚げる。
- 揚げたものをザクッと切りアツアツを食べる。
- ご飯の上に乗せて食べると、きのこどんぶりになる。そのまま食べても十分おいしい!
 肉厚でジューシーで、香りがいいこの本物のしいたけを一度食べたら、もう他のしいたけは食べられません。
肉厚でジューシーで、香りがいいこの本物のしいたけを一度食べたら、もう他のしいたけは食べられません。
「おいしさ」よりも「安さ」を選ぶ方が多いと思いますが、一度は本物のしいたけの味を味わってください。
川内村のおいしい湧き水で育ったしいたけは、もちろん無農薬です。子供にも安心して食べさせられます。 このしいたけで何度も料理をしてみたのですが、煮たり焼いたりしても縮んだりせず新鮮なのがよく分かります。
「しいたけのから揚げ」は、本当においしいので一番のおすすめ料理です。サクッと一口かじるとしいたけのジューシーな汁が口に広がります。 「しいたけってこんなにおいしかったっけ?」と言う言葉が出てきてしまいます。
鳥のから揚げよりもおいしいと私は思いますよ!!
ヘルシーに食べたい方は、簡単な網焼きですね。こちらも、しいたけの味と香りを十分に味わえます。 しいたけ好きには、この食べ方が一番ではないでしょうか?小林さんが作ったしいたけなら、きっとしいたけ嫌いの方でも、食べられると思いますよ。